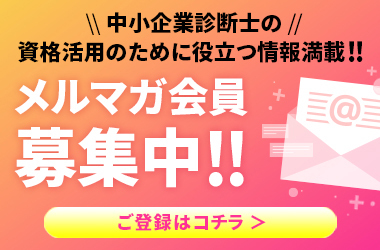先輩診断士たちに実務補習の思い出を語ってもらう企画。
今回は「M.H」様からいただきました。
この記事の目次
概要
資格登録までの道のり
実務補習5日コース+実務従事に2回参加
実務補習先企業の概要
卸売業 包装資材取り扱い 間もなく事業承継
実務補習を受ける前にやった準備
実務補習2週間ほど前には、実務補習の心得や、テキストが届きます。
事前に読んだうえで参加するよう促されます。
実務補習の5日前には、担当となる先生より、メールが届きました。
企業概要の情報や、同じ班となる方が徐々に分かってきます。
私の班では、Dropboxというファイル共有サービスを活用して3年分の決算報告書や使う様式、事前に見ておくべき資料などが共有されました。
また、事前にヒヤリング内容の検討やSWOTをしておくよう宿題が出されました。
実務補習の流れ 体験談
1日目
先生や班のメンバーと、名刺交換、自己紹介を行いメンバーのことを把握していきます。
午後には、企業に訪問してヒヤリングを行うこととなるため、ミーティングでは、ヒヤリング内容のすり合わせを行いました。
また、個々の担当を決めました。
具体的には、対応する企業が卸売系の企業でしたので、班長・経営戦略、人事・組織、営業・マーケティング、財務会計、IT、商品に分かれて、主担当と補助で分担となりました。
対応する企業により、班の分け方が異なるようです。
ヒヤリングの難しさを痛感
企業の社長にヒヤリングを行う際、ヒヤリング内容を先に端的に伝えた上で、一点ずつ伺う方法を取ったのですが、社長の話の多くが脱線していき、話を遮ることが難しく思うように聞き出すことが出来ない状況でした。
脱線した話の中で聞きたい項目が出てきたら、それを深堀りする形となってしまい、当初の計画とは違って、その場の対応力が求められることを痛感しました。
その中でも聴かなければいけないことをモレなく聴く能力の必要性を感じました。
これは、2次試験対策でも出てこない現場でのノウハウだと思います。
今までの経験でノウハウを得ている人には、簡単なことなのかもしれませんが、私には、場数を踏むことが必要と感じるヒヤリングとなりました。
ヒヤリング後に、ミーティングで内容を共有し、宿題として
- ヒヤリング内容を基にSWOTを1名がまとめて作っておく
- ヒヤリングのメモを1名がまとめて作っておく
- 各担当に該当する問題点、課題、提言、の素案と必要となる情報収集
2日目
先生により、進め方が随分異なるようで、私の班では、プロジェクターを使ったまとめ方で進めることとなり、会議室の壁の近くに陣取るよう指示がありました。
大きめの会議室に10班近く入って一斉に取り組みます。
これが複数の会議室で行われます。
ホワイトボードを使う班、模造紙にポストイットを貼っていく班、千差万別です。
1日目のヒヤリング内容の整理、共有。
ここまでは順調でしたが、SWOTを共有する際に、強みについて、漏れなく出せているか、切り口を明確にとの指示が。
ヒト・モノ・カネ・情報に区分して整理しなおすことに。
テキストも参考にしながら、モレがないかチェックしつつ、強み・弱みと整理していきます。
次に機会と脅威について、整理しつつ根拠となる調査についても併記しながら進めます。
この機会・脅威については、根拠が必要とのことで、併記していた調査項目について、何を調べるのか、どうやって調べるのかをアドバイス頂きながら、分担して2日目終了後に調査し共有することとなりました。
昼の間に報告書の様式について共有しフォームを作成。
次に、「誰に・何を・どのように」の視点で方向性を確認。
「誰に」が3パターン出てきたので、それに合わせ「何を」「どのように」とまとめたところで、時間終了。
会議室から撤収。
事前に次のミーティング場所を押さえていたのでそちらへ移動。(カラオケ店はやめておいた方がいいです。高額請求が・・・)
自主学習時のスケジュールを協議し、どのように調べるのか具体的に確認。
宿題だった各担当の調べたことの共有で、時間終了。
その後、懇親会で協力体制強化!
自主学習期間
3日目までの自主学習期間に調査と原稿作成を進めます。
ファイル共有して、先生からの指導がメールで来ることもありました。
私の場合、担当がIT化だったこともあり対象とする企業の製品に関するキーワードが、どの時期に検索件数のピークがくるか、中小企業白書にIT導入に関する統計等の資料がないか、提案できるツールはないかなど、いろんな切り口で調べ、自分のパートの原稿を進めました。
3日目
作成してきた原稿を元に、それぞれのパートを説明し、全体の方向性や提言、SWOTのブラッシュアップ、ポジショニングマップ、事業の方向性、組織人事について、商品戦略について、システムについてなどに分けて不足していることを明確にしていきました。
4日目
提案時の10分間で何を伝えるか、6人で1時間の提案をするため、その取りまとめと個人で進めていた原稿をまとめ、不足部分を修正していきます。
会場の一室にあるプリンターで原稿を打ち出して手分けして誤記等確認を進めます。
17時には、会場は完全撤収だったと思います。
そのあとで使える会議室を事前に予約して置き、そこに移動し原稿の最終調整を行いました。
その後、キンコーズへ移動し原稿の印刷を行います。
5日目
午前中に発表の練習を行い、お昼を取った後、診断先へ向かいました。
診断先では、説明前に診断先の社長に「気付いたところがあったら、メモをどうぞ」と付箋や蛍光ペンを渡してくださり、各パートの説明を行います。
診断書に付箋やメモをして下さると、興味を持っていただけたと感じることが出来ました。
滞りなく発表が終わり、みなさんで記念撮影。
開放感と共に診断先を後にします。
最後に、居酒屋さんで先生より終了証をいただき、打ち上げ。
本当に良い経験となりました。
同じ班には、地理的に近い方が集められるようで最寄り駅が近い方や同じ最寄り駅の方もいました。
この5日間という濃い時間を同じ目的で過ごしたメンバーは、その後も繋がりを持ち続ける方が多いです。
実務補習中に起きたトラブル・対応方法
1日目の夕方、時間オーバーで別の場所で続きを進める際に、会議室がすぐに見付からず、カラオケ店を利用することに。
2時間もいなかったのですが、会議室の数倍の費用に。
一人3000円以上に・・・
事前に会議室の目星をつけておき、夕方には予約をした方がよいようです。
実務補習を受けた感想(良かった点、改善点など)
調べる手段について、先生から豊富な選択肢を教えて頂いたこと、同じ目的で動いた仲間が出来たこと、地理的に近い診断士と知り合えたこと、協力して診断報告書が出来上がる慶びを共有できたことが良かった点でした。
ただ、平日に会社を休まなくてはいけないという点が、参加しにくい点になるのではないかと思います。
土日と平日夜で対応できる実務従事の方が企業に勤める方にとっては取り組みやすいのではないかと思います。
実務補習をこれから受ける方へのアドバイス(知っておいた方がいいことなど)
実務補習だけがポイントを獲得する手段ではないということを知っておいた方が良いと思います。
実務従事でポイントを獲得する方法もありますし、研究会などで支援活動を行った際に付与される方法もあります。
いろんな方と繋がりを持つと、情報が入りやすくなります。アンテナを張って、ポイント獲得手段を実務補習以外の選択肢も含めて確認していくと良いと思います。
そんな方法もあったのかと後で知るより、情報収集して自分で選択していった方がスムーズにポイントを獲得できるかもしれません。
キンコーズの会員になっていると、印刷が割引になるようです。
先生用と診断先用はカラーで製本し、メンバー分は白黒で製本無しという手もあります。
その方が早く費用も安かったので、その方法でまとめました。
印刷費用は一定額の補助があったと思います。
キンコーズなどの印刷屋さんは、4日目の夜に非常に混雑します。
なるべく早く原稿を仕上げて、持っていくよう意識することと、複数のキンコーズを確認しておくことが良いと思います。
実際、問い合わせると出来上がりが翌日になるケースもありました。
中小企業診断士のための実践コンサル塾事務局
最新記事 by 中小企業診断士のための実践コンサル塾事務局 (全て見る)
- “いま”身につけたいスキルアップ講座「イマスキ講座」スタート - 2024年3月27日
- YouTubeの登録者数1,000人まであともう少し・・・ - 2023年12月26日
- 8月スタートの”実務従事サービス”申込受付中です! - 2023年7月29日
- 「診断士なら知っておきたい!DX支援の基礎」セミナーの受付開始 - 2023年3月6日
- 「はじめての補助金セミナー 現場で使える補助金ノウハウ」の受付開始 - 2023年3月1日